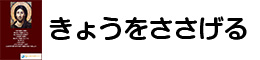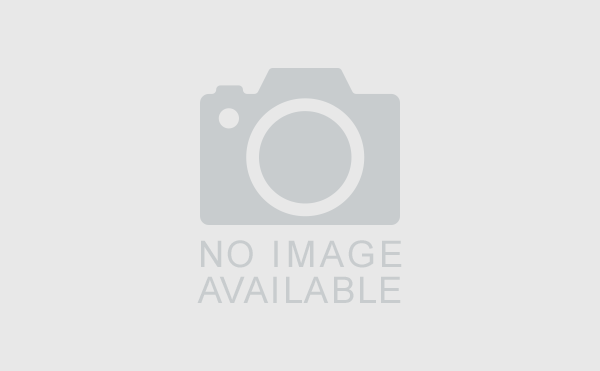2025年10月 4. SAF
日本の教会は今月の意向として「被造物、すべてのいのち、自然環境」を取り上げて、前教皇フランシスコのメッセージを受けとめて環境を保護するように呼びかけています。
私たちの社会は、交通と通信の発達によって、世界が狭くなりました。江戸時代には、江戸から京都までに宿場町が53あり、これを東海道五十三次と呼んでいましたが、徒歩でおよそ2週間の旅だったようです。今では東海道新幹線で東京駅から京都駅まで、およそ2時間10分で行くことができます。
交通機関で最も高速なのは、航空機による空の旅で、羽田空港から伊丹空港までは、約1時間のフライトです。この高速で便利な空の便は、実は輸送単位あたりの二酸化炭素排出量が最も多い乗り物です。そのために、脱炭素社会の実現に向けては、喫緊の大きな課題のひとつになっています。そこで、切り札となって登場したのが、表題に掲げたSAFです。
SAFとは、「Sustainable Aviation Fuel(持続可能な航空燃料)」の略称で、循環型の原料から製造されます。通常ジェット機などで使用されている燃料は、化石燃料である原油を精製して作られます。一方SAFの原料は、地球上で育った植物が原料として用いられているために、過大な二酸化炭素の放出を行わないことで脚光を浴びているのです。二酸化炭素は光合成によって大気から植物の中に蓄えられ、それが燃焼によって空気中に再び放出される、つまり循環するわけですので、過去に石炭や石油に閉じ込めた炭素を今の時代に燃焼して空気中に放出して二酸化炭素の量を増加させるのと比べれば、カーボンニュートラルを実現するために有効であることは自明です。
SAFの製造方法は、飲食店などから排出される廃食油と水素を使ったもののほか、とうもろこしやさとうきびを発酵させてつくったアルコールから作るもの、藻や古紙などから油分を取り出し水素を使ったり発酵させてつくったアルコールから作るもの、ごみなどの原料を蒸し焼きなどにしてガス化し、炭素1個の分子と水素分子にばらばらにしたあと、再びつなぎ合わせて液体燃料を製造したもの、二酸化炭素と水素を合成して製造するいわゆる合成燃料などがあります。いずれの製造方法は確立されているのですが、コストが高すぎたり未だ実証段階だったりで、課題は山積しています。
その中で、今日実用化に至っているのは、廃食油から作られたSAFです。スーパーマーケットや飲食店で使用した食用油や植物油を集める仕組みが、少しずつ整えられてきました。家庭から出た廃食油を回収するスポットも増え始めています。
食品トレイや牛乳パックは、今やどのスーパーマーケットでも回収拠点となっています。やがて廃食油の回収拠点が町中に広がるようにと、祈り願ってまいりましょう。