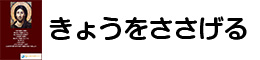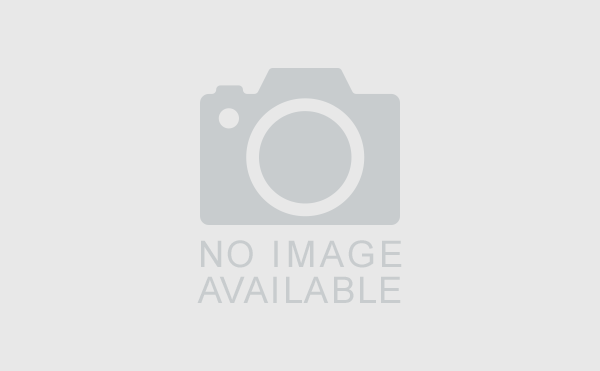2025年2月 4. 精神障害と自死
日本の教会の意向は「病者」で、それを「キリストの受難に合わせて忍耐をもって苦しみを捧げる」者と、表現しています。自分から好んで病気になる人は、誰一人としていません。そして、万全な予防策を施したとしても、罹患しないことが保証されるわけではありません。ですから、医療処置を受けることはもちろんですが、病気になったことを受け入れるほかに、手立てはありません。
今日の社会で「忍耐をもって苦しみを捧げる病者」のひとつに、心の病をあげることができるでしょう。病の苦しみばかりではなく、社会が抱く偏見によっても苦しみは一層大きなものでしょう。精神疾患は、人柄や性格に起因するものではなく、脳の病であることが医学的にはっきりとしていますが、「気違い」ということばを使っていたこともあって、偏見や差別はなかなか解消されません。心の病にかかっている人を「病者」として認識し、他の病と同じように受け止めることが大切です。
病が進行してやがて死に至ることもあります。2023年の厚生労働省の人口動態統計によると、がんによる死亡率は全死亡数の24.3%で、およそ4人に1人ががんで亡くなっています。心の病の場合には、身体に影響があらわれて死に至ることはありませんが、さまざま要因が複雑に絡み合って、自死や事故死に至ってしまうことがあります。世界保健機関(WHO)の発表によると、自死で亡くなった人の9割が精神障害を患っていました。
キリスト教は、伝統的に自死を罪としてきました。ですから、第二バチカン公会議以前には、自死した人の葬儀を教会で執り行わないこともありました。しかし、精神疾患についての新しい理解に基づいて、日本カトリック司教団は『いのちへのまなざし【増補新版】』で「自らの意思で死を選ぶというよりも、死ぬしかないところまで追いつめられた末の死」と表現して、個人の問題としてではなく、社会の問題として取り扱うようになりました。
愛する人の死は、とてもつらく悲しいものです。たとえそれが自死であったとしても、その深さは変わりません。精神疾患の後に死に至った人を「忍耐をもって苦しみを捧げる病者」として理解し、分け隔てのない心で、天の国への旅立ちをお祈りいたしましょう。